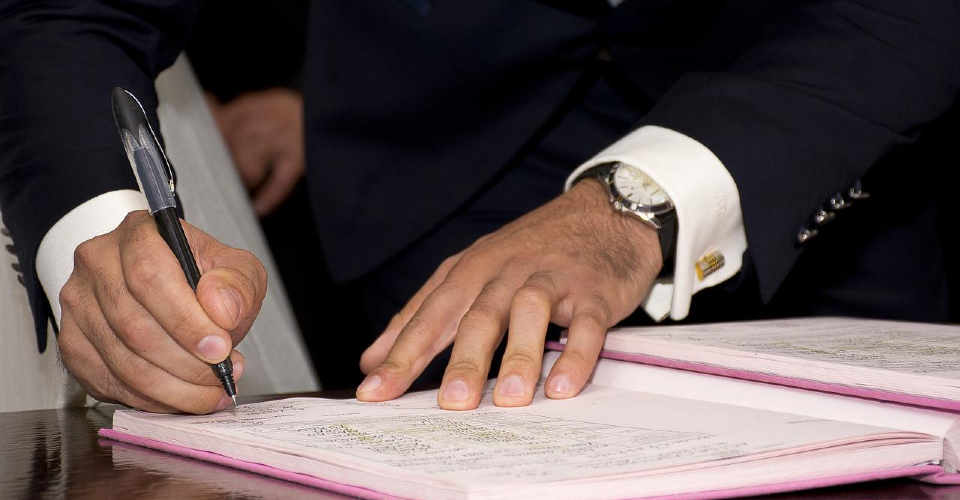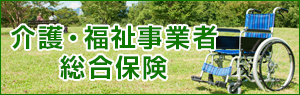寝たきり介護が必要になる要介護度とは?ケアする上で注意したいこととは

寝たきりの状態が続けば、体を動かす機会もだんだんと少なくなり、体力や筋力は低下してしまいます。
それにより、内臓など機能しなくなり、運動器障害や循環・呼吸器障害、自律神経・精神障害といった症状が見られるようになるでしょう。
思うように身体を動かすことができない状態では、自らで動こうとする意識も低くなり、さらに寝たきり状態が進んでしまうという悪循環に陥りがちです。
高齢者の場合には、寝たままの状態が1週間続けば約10〜20%の筋力が低下するともいわれていますが、寝たきり介護が必要になる要介護度や、ケアする上で注意したいことについて解説していきます。寝たきり介護が必要になる要介護レベル
寝たきり介護が必要とされる要介護レベルは、要介護4または5です。
寝たきり状態で意思疎通が完全にできなくなっていると、要介護5の認定になるケースが多いといえます。
要介護4以上では、介護がなければ日常生活を送ることは困難な状態となり、食事・排泄・入浴などの日常生活全般で介護が必要となります。
寝たきりの状態が続けば、床ずれが起きるリスクが高くなるため注意しなければなりませんが、在宅介護では常に介護を必要とする状況の中、家族の介護負担が増えれば介護疲れなどでストレスを抱えてしまうリスクも高まります。
利用できる介護保険サービスなどを活用し、寝たきりの高齢者の方だけでなく、介護を担当する家族も安心して生活を送ることができるようにしましょう。
寝たきり介護で注意したいこと
寝たきり介護で注意しておきたいこととして、主に4つが挙げられます。
・床ずれ・褥瘡の予防・ケア
・排泄介助への気配り
・要介護者の清潔保持
・介護者側の負担軽減
それぞれ説明していきます。
床ずれ・褥瘡の予防・ケア
寝たきりの方は、自分で身体を動かすことや、姿勢や体勢を変えることは難しいといえます。
しかし身体を動かさない状態で同じ姿勢が続けば、身体の一部に圧力がかかることとなり、血行不全や周辺組織壊死などで「床ずれ」や「褥瘡」が発生します。
床ずれや褥瘡を避けるためにも、定期的な体位変換と適切なケアが必要です。
排泄介助への気配り
寝たきり状態の方は、一人でトイレまで行き排泄することは困難なため、専用トイレやおむつなどを使用します。
介護者の負担になりやすい介助ですが、要介護者の精神面や尊厳に関わる部分でもあるため、気配りは忘れないようにしましょう。
要介護者の清潔保持
寝たきり状態の方は、全身入浴する機会や着替える頻度は少なくなりがちです。
身体や周辺環境を清潔にすることが難しくなるものの、清潔さをできる限り維持できる工夫は必要といえます。
介護者側の負担軽減
寝たきりの方を介護することは介護者の精神面や肉体に大きな負担となるため、負担軽減のためにも介護保険サービスなど活用しながら、自分の時間も作るようにしてください。