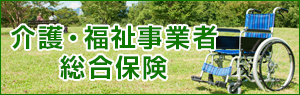海外で介護サービスを提供する介護事業者の特徴

医療技術が進歩してきたことにより、平均寿命も延びたことから介護を必要とする方の人数も増えています。
日本だけでなく世界でも同じ動きが見られますが、その中でも日本はトップクラスの長寿大国とされているため、高い質効率的な介護対策を急務としているといえるでしょう。
そこで、日本の介護における問題を分析するために、海外などの取り組みについて知っておくようにしましょう。
海外の介護事情は国によって異なる
日本で今行うべき介護対策を考える前に、海外での介護政策について把握しておきましょう。
スウェーデン
スウェーデンは福祉大国と呼ばれるほど、国が積極的に介護サービスを提供している国です。1970年代から高齢者福祉が実践されており、計画的に介護政策を実行していることが特徴といえるでしょう。
地方自治体などのコミューンを中心として、在宅介護サービスや訪問ケアサービスを充実させ、ホームヘルパーの公的地位も安定しています。
高齢者は住む場所を変えることなく自宅で生活しやすくなっています。
ドイツ
ドイツは日本と似たような厳しい状況にありますが、世界で社会保険の仕組みを初めて作り介護保険の導入を始めた国です。
ドイツの介護制度は在宅介護を優先させる方針となっているため、日本が目指す地域包括ケアの手本になっているとも考えられます。
イギリス
公的年金の支給額が低く、老後の経済的基盤づくりを支援するため年金の繰下げ制度が設けられているのがイギリスの特徴です。
そしてイギリスでも在宅ケアを重視する傾向が強く、地方自治体が民間会社にサービス提供を委託するなど、多様なサービスの質を高めています。
デンマーク
北欧の小国であるデンマークは、寝たきり患者がほとんどいません。その理由は、デンマークでは特別養護老人ホームに似たプライエムが多数存在していたものの、今は新規建設を禁止しており在宅介護を重視する方向へと転換させているからです。
在宅介護でも訪問介護スタッフは必要であれば無料で何度でも訪問することになっており、サービスを利用する高齢者の既存の能力や自己決定能力を活性化させていることにつながっているといえます。
さらに自治体や病院が責任を持ちながら、高齢者に合った住居や治療を提供することも義務化されていることが魅力です。
アメリカ
ベビーブーム世代の高齢化が始まっていますが、アメリカには日本の介護保険制度のような公的制度はありません。
そのため民間の保険に加入している方など、限られた方のみが施設を利用しています。ただ、低年収の方を対象として、食事や身体ケア、ハウスキーピングなどのサービスが利用できるサポート付き住居はあります。
高齢者が住みやすい住宅を整備する動きが活発化している国といえるでしょう。