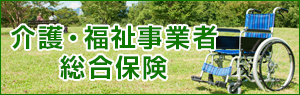介護事業者が知っておきたい老人の増加により起きる重大な問題

介護は現代の日本社会が抱えている大きな課題の1つといえますが、超高齢化社会では介護者も高齢となるため、高齢者が高齢者の介護を行う老老介護などの様々な問題が起きやすくなっています。
そこで、老人の増加により今後起きやすくなると考えられる「介護難民問題」や「老老介護」について説明していきます。
介護難民問題
老人の増加により危惧されているのが「介護難民問題」です。
介護を必要とする要介護者として認定を受けているのに、施設に入所できない状態や、求める介護サービスの利用ができないなど、介護サービスを受けることができない65歳以上の高齢者を「介護難民」といいます。
2025年になると、全国で約43万人の介護難民が発生するといった予測もあるなど、高齢化が今後進むことで誰でも当事者になる可能性がある問題です。
介護難民問題が起きるのは、高齢化が進み要介護者数の増えることが原因と考えれます。
それに加え、介護現場で働く介護従事者が不足しているため、需要と供給がおいつかず介護難民を増やしてしまいます。
特に「東京圏」と呼ばれる東京近辺一都三県は介護難民が増えると予想されています。
介護難民問題解消に向けた国の対策
介護難民問題を解決するために、国が打ち出した対策が「地域包括ケアシステム」です。
高齢者を地域全体でケアしていこうという考え方であり、地方自治体の「地域包括支援センター」が中心になって運営します。
施設や医療機関の紹介、介護相談にも応じてもらえるなど、自分は介護難民かもしれないと感じる高齢者の不安を解消することができます。
老老介護が増える問題
65歳以上の高齢者が65歳以上の高齢者を介護している状況が「老老介護」です。
夫婦間の年齢は近いことが多いため、夫が高齢なら妻も高齢であり、介護が必要になった夫のケアを妻が行うケースなどが該当します。
親と子が別に住む核家族が一般化したことで、高齢者夫婦世帯で夫か妻のどちらかが介護を必要とする状態になったとき、在宅介護では必然的にどちらかが介護を行うことになるでしょう。
また、平均寿命も延びたことにより、高齢の親の面倒を高齢の子がみるといったケースも含みます。
老老介護を増やさないための対策
老老介護対策で重要なのは、介護を必要とする状態にならないようにすることといえます。
認知機能と運動機能を保つ努力をし、自分の意志を明確に残すことができるように、早めに家族観で万一要介護状態になったときについて話し合いをしておきましょう。
地域の方たちとの交流も積極的に行い、不安があるときには早めに病院を受診して、疾患や障がいの早期発見に努めることも大切です。