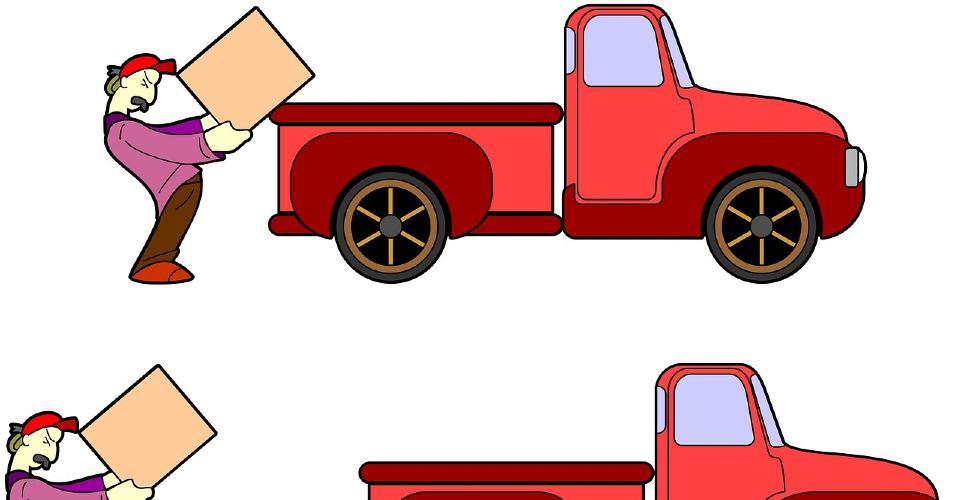物流業界を改善させるために荷主だけができることとは?

物流・運送業界では、輸送・保管などの物流業務を依頼した主を荷主と呼んでいます。荷物の出し手のことは発荷主、反対に受け取り手を着荷主と区分することになりますが、これまで物流業界は発荷主を意識した仕事の傾向が高かったといえます。
しかし今は着荷主のニーズに着目し、耳を傾け対応できるような動きが大きくなったといえるでしょう。
物流業界の改善に荷主の協力は欠かせない
荷主があってこそ、物流の仕事は発生するといえますが、一般的にメーカーや小売店などを指している言葉です。ただ、モノを運ぶ経緯において運送業務の元請から下請へ発注があれば、元請も下請にとっては荷主という関係になります。
物流業界を改善させるためには荷主の協力は必要不可欠であり、物流業者のみの自助努力だけでドライバーなどの労働時間を短縮させることはできません。
実際、請負構造により運行管理が適切でないという背景を改善させようと、2019年には厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」のガイドラインも策定されています。
ドライバーの長時間労働をなくすため荷主にできること
厚生労働省では、トラックドライバーが発荷主と着荷主からの依頼や要望に基づき輸送を行っていることを踏まえ、荷主にしかできないドライバーの労働時間削減について次のような取り組みを挙げています。
運送事業者への運送委託の見直し
発荷主から運送事業者に対する運送委託の内容そのものがドライバーの長時間労働につながる原因になっているとし、運送委託の見直しの必要性を訴えています。
着荷主への働きかけや協力を求めること
着荷主のいろいろな納入についての要件がドライバーの長時間労働の原因につながっているとし、要件を見直す着荷主に対する働きかけも必要としています。
荷揃えなど倉庫の仕組みの見直し
荷扱い作業や付帯作業などが倉庫で発生すれば、トラックドライバーは長時間労働を強いられることになる可能性もあります。それに加え、待ち時間があれば労働時間はどんどん延びることになるでしょう。そのため、これらの作業時間を削減することが必要とし、荷主だけができる取り組みとして挙げています。
荷主にだけできる取り組みを実行するメリット
具体的には運送委託の締め切り時刻の見直しや、運送委託の追加・変更を削減すること、さらに運送委託の物量の見直しなどが取り組みとして有効と考えられます。
運送委託を見直すことは手間や時間がかかることですが、配車が最適かされれば納期遅れもなくなり、結果として荷主にもメリットがあるといえるでしょう。