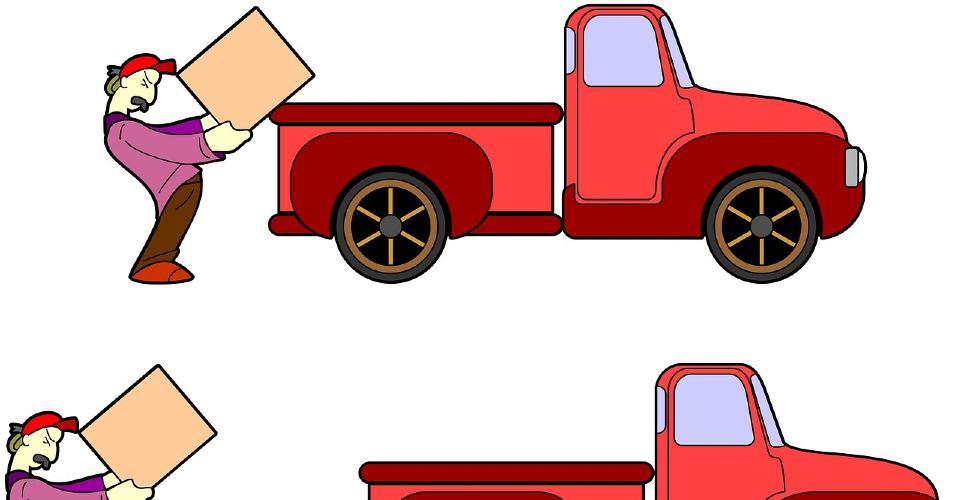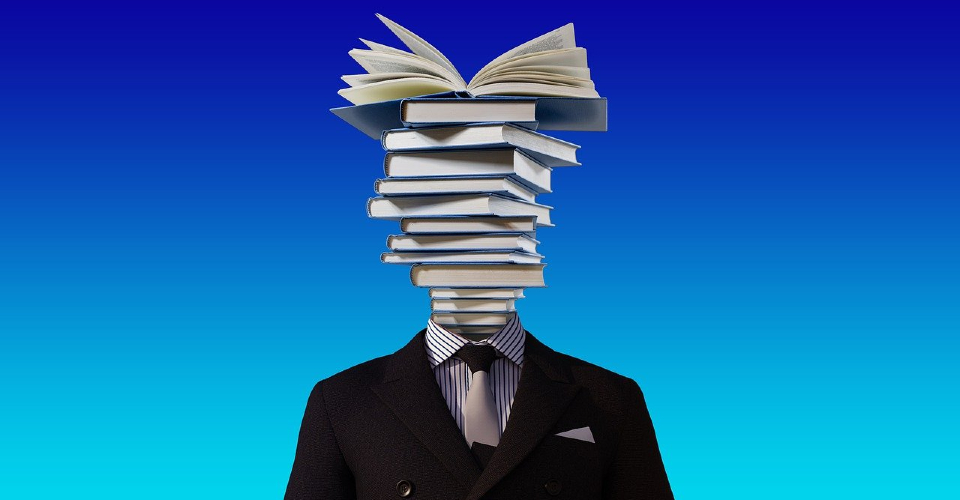運送中に爆発などの危険があるものを運ぶときの決まり

運送中、爆発などの危険がある危険物や毒物などの運搬は、その種類や陸・海・空などの運搬方法により、規制される国内法令が違ってきます。
消防法や関連法規では、主にトラックで運搬することを想定した内容となっていますので、具体的にどのような決まりになっているのかご説明します。
指定数量による規制と混載禁止について
陸路における危険物や毒劇物の運搬・運送は、まず指定数量による規制と類別による混載禁止について規定されています。
・指定数量以下の場合には、高圧ガスとの混載を禁止する
・指定数量10分の1以上の場合には、高圧ガス・類を異にする物品の混載を禁止する
・指定数量以上の場合には、高圧ガス・類を異にする物品の混載禁止の他、危険物の標識を車両の前後に提示し、運搬する危険物に適応する消火設備が必要
なお、類を異にする物品の混載禁止とは、同じ車両で異なった種類の危険物を積載することを禁止するという意味です。
危険物の標識とは
車両に掲げなければならない標識とは、0.3メートル平方の黒色の板に黄色の反射塗料または反射性のある材料により「危」と表示したもの、または0.3メートル平方の黒色の板に、白色で「毒」と表示したものです。
これらの表示がされた標識を、車両の前後の目につきやすい場所に掲げなければなりません。
万一運送事故が起きたときのために
毒物・劇物を運搬するときには、万一運送事故が起きたときに備え、応急処置を適切に実施できることを目的に事前の情報伝達と備えを義務づけています。
1千キログラム超の毒物・劇物の運搬については、成分や事故が発生したときの応急処置法など、イエローカードを交付し通知することが義務づけられています。
下請け・孫請けの運送会社に委託する場合でも、徹底して行うようにしましょう。
5千キログラム超の毒物・劇物の運搬については、次の項目を参考にしてください。
・事故の応急処置方法を記載したイエローカードを携行すること
・毒標識を掲示すること
・毒物・劇物ごとに対応した保護具の2人以上の備え付けが必要
・一定時間を超えた運転が必要な場合の交代要員が必要
イエローカードとは
緊急連絡カードのことをイエローカードといい、化学物質の有害性や事故が発生したときの応急措置の他、緊急連絡先などが記載されています。
万一事故が発生したときの応急措置対策を強化するためにも、危険物・毒物・劇物のときに活用します。