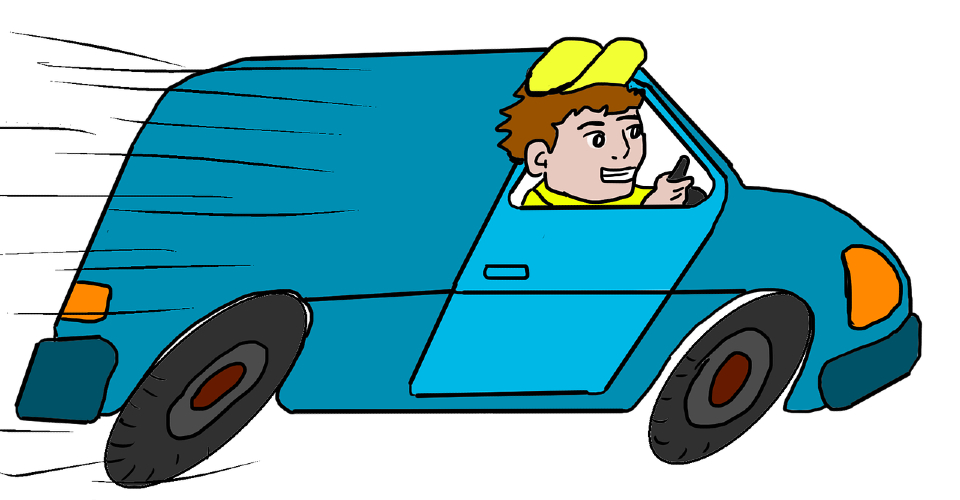物流に関連するAIやドローンなどは国益を守るための重要な技術

情報通信分野の技術革新が進んだことで、企業活動は国家の安全保障に密接に関係するようになりました。
国益を確保するため政府も戦略的な取り組みを行うことが欠かせない状況ですが、国家安全保障会議の事務局である国家安全保障局に経済担当の新部署を設けるなど、安全保障が絡む通商政策を強化する動きも見せています。
米中の争いも激しさを増す中で
様々な産業で人工知能AIやビッグデータが普及され、変革をもたらしています。この技術面で優位性を保つための米中の覇権争いも激しさを増しており、新型コロナウイルスの感染源が中国にあるとしてアメリカも様々な法整備を進めているようです。
中国は民間技術を活用しながら国防力を強化する軍民融合を図り、通信機器大手のファーウェイなど中国企業でも次世代通信規格5Gを先行整備しています。
アメリカはファーウェイを安保上の脅威であるとして米企業取引を禁じ、重要技術の輸出管理を対象とした法整備も進めています。
日本が行わなければならないこととは
日本も通信機器の政府調達に関して指針を定め、外部に流出するリスクが高い機器などを排除しました。
外国人投資家などの日本企業に対する投資も規制し、宇宙や原子力など安全保障に関係する分野においての情報が窃取されることを防ごうとしているようです。
実際、大学や研究機関における情報管理は甘いとされており、技術が流出してしまう仕組みを構築すること急務といえるでしょう。
さらに取り組むべき課題とは
民間の経済活動や研究開発に過度に介入すれば、健全な競争を阻害しかねない。安全保障政策と、企業の競争力確保のバランスに留意する必要があろう。
政府は国産ドローンが普及されることを後押ししようと、開発予算を支援する法案なども提出しています。
ドローンの国内シェアは中国製のものがその大半を占めており、災害や物流など幅広い分野に普及していくのにつれて、不正に情報収集されたり重要施設に攻撃されたりするのではないか?といった懸念も高まっているようです。
新型コロナウイルスの感染拡大により、中国から部品調達が滞ってしまったことを理由に、自動車メーカーなどは減産するしかない状況となっています。
生産拠点が過度に偏ってしまうことで、産業の基盤が安定しなくなるリスクがあると認識し、部品を供給するサプライチェーンを多様化することが今求められているといえるでしょう。