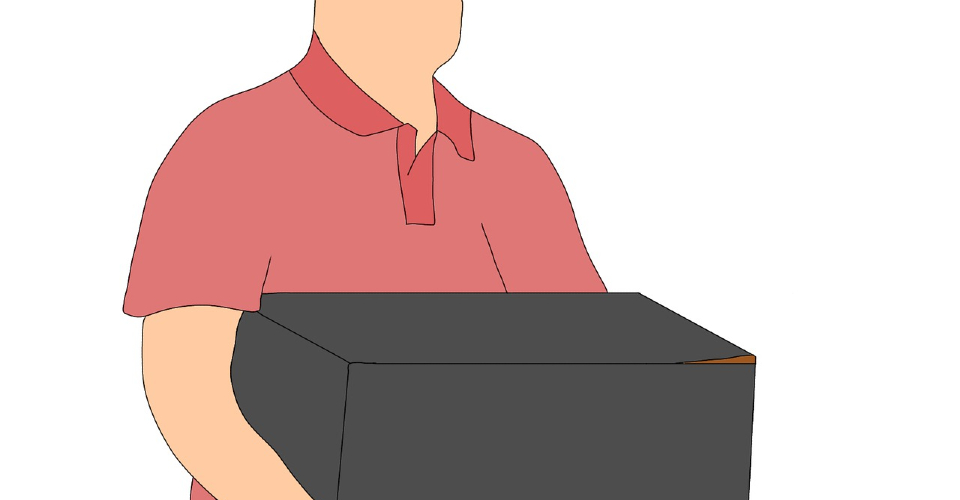物流業界に関係する郵政省から日本郵便までの歴史とその事業の仕組み

かつて日本の行政機関として存在していた郵政省は、国家行政組織法と郵政省設置法に基づいて、郵便事業・郵便貯金事業・簡易保険事業・電気通信・電波・放送に関する行政を取扱っていました。
物流業界でも大きく関係するのが郵便事業ですが、2001年1月5日に行われた中央省庁再編により、総務省と郵政事業庁となっています。
日本の郵便の仕組みは1871年(明治4年)に誕生しましたが、その歴史をご紹介します。
もともと日本で郵便の仕組みを作ったのは?
日本で郵便の仕組みを作ったのは元官僚の前島密氏で、イギリスの仕組みを手本としたものでした。
郵便の仕組みができるまでは、手紙や品物は飛脚に費用を支払い頼むことが一般的だったのですが、国が責任を持ち配達する仕組みを構築したのです。
郵便の仕事を行う逓信省が誕生し、逓信とは順番に通信を取り次ぐという意味を持っています。なお逓信省は1949年に郵政省に名称が変更されました。
しかし郵政省は省庁改革に伴って、2001年から総務省の郵政事業庁に引き継がれることとなり、2003年4月に日本郵政公社が始まります。公社とは国でも民間でもない特別な会社であり、国は公社に対して責任を持つものの経営には口を出さないという中間的な立場となります。
ただし郵政公社のトップは総務相が任命する総裁であり、職員は国家公務員のままという状況です。独立経営体なので人事や給与制度は役所とは異なります。
手紙を出す人は減っているのに日本郵便はなぜつぶれない?
現在は民営化された日本郵便ですが、インターネットが普及したことで年賀状を出す人も減っています。この手紙やハガキなどの郵便物はメールなどで代用できるようになったため、日本郵政の郵便物取扱件数は減少の一途を辿っている状況といえるでしょう。
人口が極めて少ないエリアでも郵便局は存在していますが、運営コストは売上よりも高くなるはずです。
それでも補助金に頼らず会社として事業を成り立たせているのは、郵便事業だけではなく金融窓口事業も営んでいるからです。銀行窓口業務や保険窓口業務なども行い、日本郵便はそこから手数料を得ています。
利益率は高くなくても郵便事業での損失をカバーできる金額なので、郵便事業だけでは儲けを出すことはできなくても、郵便物を出すついでに公的年金などの支払いをしたときに投資信託や保険などを勧められ加入する方もいるようです。
単一の事業だけでは儲けを出すことはできなくても、続けることにより他の事業の商品を販売できる仕組みを作っているからこそ今があるといえるでしょう。