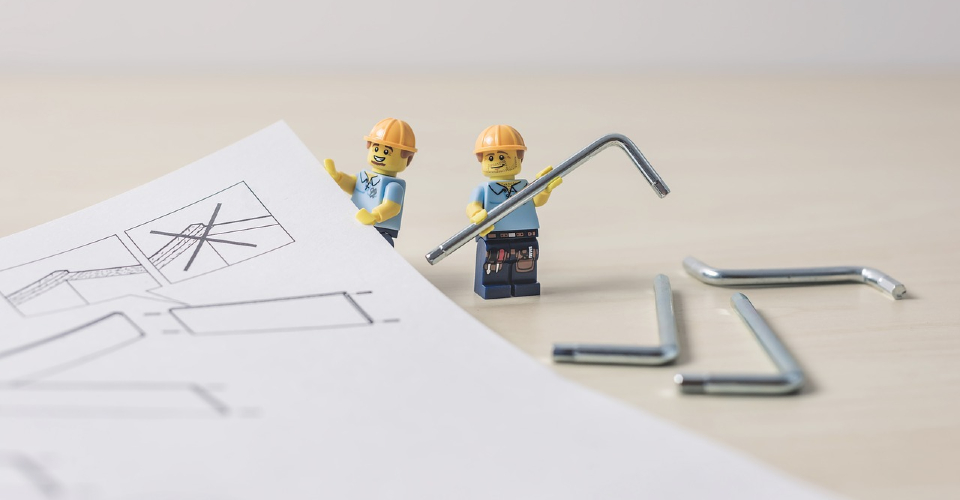建設工事現場で欠かせない「危険予知活動」や「危険予知訓練」とは

建設工事現場では、現場の作業方法・機械設備・作業環境などを見ながら、いつ・どのようなときに危険なのか事前に把握しておくことが必要です。
たとえばイラストなどを確認しながら、作業に潜む危険有害要因を特定することや、危険への対策について全員が本音で話し合って安全を先取りする活動が求められます。
このような活動を「危険予知活動(KYK)」や「危険予知訓練(KYT)」といいますが、具体的にどのような効果があるのか、その内容について説明していきます。
「危険予知活動」を行うことで期待できる3つの効果
建設工事現場で「危険予知活動」を日々継続して行うことにより、現場の作業者は危険なことを「危ない」と感じる感覚や、危険に対する感受性や集中力を高めて、問題を解決する意欲や安全作業実行能力を向上させることが可能です。
災害発生に至る要因のうち、現場で対応できる「不安全行動」を回避すること意図したものが「危険予知活動」といえますが、主に次の3つの効果が期待できます。
危険に対する感受性を鋭くすることができる
繰り返し行うことにより、危険なことを「危ない」と感じる感覚や、危険に対する感受性を高め鋭くすることができます。
安全作業に対する集中力を高めることができる
危険性の高い作業のうち、より大事な部分で「指差呼称(指差唱和)」を行うことにより、安全作業に対する集中力を高めることができます。
問題解決能力を高めることができる
作業の中にどのような危険が潜むか、危険有害性に対する話し合いを行うことにより、危険なことを危ないととらえながら実践する意欲や、問題解決能力を高めることができます。
「危険予知活動」の進め方
危険予知活動の種類はいろいろありますが、作業状況の中にどのような危険が潜むか、次の4つの段階で実施していく方法が進めやすいでしょう。
どのような危険が潜んでいるか現状を把握する
・危険要因は掘り下げる
・危険要因を具体化する
・危険の様子を肯定的な表現であらわす
・事故の型を言い切る
作業の一定手順の場面を決めておき、対象となる作業に対し予測される危険を全員に発言してもらうようにし、できるだけ数多く項目を出すことを心掛けましょう。
危険のポイントとなる本質を追及する
危険のポイントを絞り込み、より重要と思われる項目を1~2つ選び、「危険のポイント」として「指差呼称」します。
危険のポイントについて対策を立てる
「危険のポイント」についての対策をリーダーから全員に問いかけ、実行可能な対策は「~する」といった能動的な表現で発言します。
危険に対する目標を設定する
対策を絞り込み、全員から合意を得て1つの項目に絞りこみます。絞り込んだ対策は重点実施項目の「チーム行動目標」とし「指差呼称」しましょう。