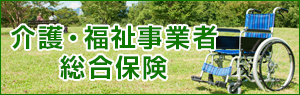団塊世代が75歳以上になる2025年問題とは?懸念される介護難民を防ぐポイント

第一次ベビーブームの時期に生まれた団塊世代は、2025年に75歳以上となり、いよいよ超後期高齢者社会へと突入します。
介護保険制度の持続が懸念され、介護保険料は上がり続けていますが、今後は介護サービスを利用したくてもできない介護難民が増えることも懸念されます。
そこで、団塊世代が75歳以上になる2025年問題とは何なのか、懸念される介護難民増加を防ぐポイントについて解説していきます。
2025年問題とは
「2025年問題」とは、日本の人口のボリュームゾーンといえる「団塊世代」が75歳以上の後期高齢者になる2025年の構造変化のことです。
日本の平均寿命は男性81歳、女性87歳と年々延びていますが、日常生活を問題なく遅れる健康寿命は一般的な平均寿命よりも9~12歳前後低くなり、男性72歳で女性は75歳となっています。
平均寿命を延ばすことよりも健康寿命を延ばすことが長寿化社会では重要なことであり、2025年に後期高齢者が増える前に、多くの方が健康な状態を保っていることが望ましいといえるでしょう。
しかし実際には介護を必要とする方が増えると予想される、団塊世代の子世代である第二次ベビーブームの「団塊ジュニア世代」も50歳を超えます。
人口の多いこの2つの年代層が老いと介護に向き合わなければならなくなるのが2025年であり、本格的な超高齢社会へ突入することを意味しています。
共働き世帯増加でヤングケアラーも増加
夫婦が共働きである世帯は一昔前と異なり当たり前になってきました。
そのため家族の誰かが介護を必要とする状態になっても、子世代が対応できず孫世代にまで影響を及ぼしつつあることも問題です。
ケアする側は外に出て働いているため、働いていない10代の孫が介護を担当するなど、「ヤングケアラー」という言葉が注目され始めています。
孫などが介護を担当することになれば、責任や負担を重く感じるだけでなく、学業や友人関係にも影響が出る可能性があります。
介護で仕事を辞めなければならない
親の介護を理由に、仕事を続けることが難しいと感じれば、退職するしかなくなります。
本人は仕事を続けたくても、会社に迷惑がかかるといった理由で辞めてしまうケースもありますが、経済的に困窮してしまいます。
2025年問題を過ぎた先の20年は、これまでの20年と構造的な違いがあることを理解し、自分のこととして直面する時代に突入したと考えておくべきでしょう。