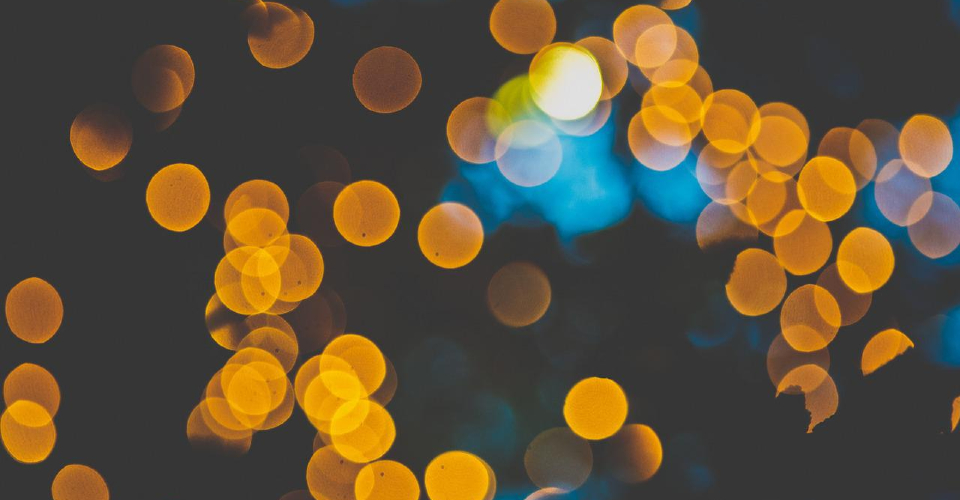建設工事は長時間労働に注意!2024年4月から適用される労働時間上限規制のポイント

2019年4月に法律が改正され、労働時間の上限が規制されるようになりました。
中小企業は2020年4月から適用対象となり、長時間労働を強いられる労働者が少なくなることが期待されます。
建設業の場合は長時間労働の傾向が強く、すぐに労働時間上限規制に対応できないと考えられため、2024年4月まで特例で適用が延長されていますが、数年後には対応しなければなりません。
ついに建設業でも残業上限規制が2024年4月から適用
労働時間上限規制については、建設業では一定期間の猶予が与えられています。
しかし2024年4月からは、建設業でも適用対象となるため、今からできる対応はしておく必要があるでしょう。
罰則付きの規制なので、これまで時間外労働を多く要請していた場合でも、労働時間の上限規制を遵守した労働が必要となります。
長時間労働が建設業の猶予期間適用の背景に
建設業の場合、長時間労働が常態化しているため、すぐに労働時間の上限規制に対応できないと考えられたことから、一定の猶予期間が設けられています。
1週間に1日休みを取ることができない、4週4休以下の就業というケースもめずらしくなく、短納期なのに人手不足といった状況が長時間労働に拍車をかけているといえます。
建設業の時間外労働上限規制の内容
2024年4月から建設業も適用される労働時間の上限規制は、原則として労働基準法に定められている労働時間の上限である1日8時間・1週間に40時間は順守する必要があります。
建設業ではこの上限を超えた労働が必要になるケースが多いため、労使間で「36協定」を結んでいることがほとんどでしょう。
「36協定」は、労働者に時間外労働や休日労働をしてもらうとき、事前の届出が必要となる協定です。
協定を結んでおくことで、1か月45時間・1年間360時間を上限とした時間外労働が可能となります。
ただ、納期が差し迫った状態では、この上限も超えた時間外労働が必要になるケースも考えられます。
その場合には、「特別条項付き36協定」を労使間で結ぶことで、労働時間の上限を引き上げることが可能です。
しかし、これまでは特別条項に上限時間がありませんでした。
しかし働き方改革では、この「特別条項付き36協定」に超えることのできない上限規制が罰則付きで設けられています。
特別条項付き36協定を結んだ場合でも、休日出勤を含めて月100時間未満・年間720時間以内までの時間外労働の上限を守らなければならないという内容です。
さらに、36協定の上限である45時間を超えた労働は年間6回までとなり、複数月の平均は休日労働を含め80時間以内に収める条件も満たすことが求められます。
36協定による残業規制の適用除外
なお、特別条項付き36協定の労働時間の上限規制については、建設業では災害復旧や復興事業に従事するときは除外されます。
年間最大720時間は遵守しなければなりませんが、月最大100時間未満と、2~6か月の月平均80時間以内の規制は適用されません。
ただし割増賃金の支払い義務は免除されませんので、注意してください。