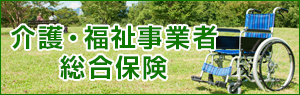訪問介護事業を開業後に重要となる緊急時の主治医との連絡について

訪問介護事業を開業する際の運営基準は、事業開始において介護事業所が行わなければならないことや留意すべき事項など、運営上のルールです。
その中に、緊急時の主治医との連絡についても記載がありますが、他にもどのような重要事項があるのでしょう。
そこで、訪問介護事業を開業後に重要となる緊急時の主治医との連絡や、その他重要事項も含めて紹介していきます。
運営基準にも主治医への連絡に関する記載あり
訪問介護事業は、利用者やその家族に運営規程の概要やサービスなど、重要事項を文書で説明・交付することが必要です。
利用者やその家族から同意を得てから介護サービスの提供をスタートすることになりますが、運営基準は提供サービスによって異なる場合もあります。
訪問介護の運営基準は、主に以下のとおりです。
・サービスの提供内容および手続の説明・同意
・提供拒否の禁止
・被保険者資格・要介護認定の有無および要介護認定の有効期間
・サービス担当者会議等を通じた心身の状況など
・サービスの提供の記録
・利用料などの受領
・訪問介護計画の作成および利用者の同意
・利用者に関する市町村への通知
・利用者の病状の急変など緊急時における主治医への連絡など
・事業運営に関する重要事項の運営規定
・介護等総合的な提供
・訪問介護員などの健康状態の管理・設備・備品などに関する衛生管理
・苦情を受付窓口の設置などで必要な措置・記録
・事故発生の際の市町村・利用者家族・居宅介護支援者などへの連絡など必要な措置・記録
など
緊急連絡手段の準備が重要
在宅介護の場合、要介護者が急変したときや事故に遭ったとき、発見してもらえない状態は避けなければなりません。
要介護者自身が自力で助けを呼べない可能性もあるため、次の方法で外部と連絡を取ることができる準備が必要です。
・手が届く場所に電話の子機を置いてもらう
・緊急通報装置を利用してもらう
・見守りセンサーを活用してもらう
・リスト化した連絡先等を貼ってもらう
それぞれ説明していきます。
手が届く場所に電話の子機を置いてもらう
ベッドや移動の際に通る廊下など、電話機の子機を設置しておくと安心です。
緊急通報装置を利用してもらう
ボタンを押せば外部と連絡できる緊急通報装置を利用すると、介護事業者や看護師とつながりやすく安心です。
見守りセンサーを活用してもらう
見守りセンサーがあれば、利用者本人の動きや消費電力などを検知でき、異変に気がつきやすくなります。
リスト化した連絡先等を貼ってもらう
万一の際にどこに連絡するべきか迷わないようにするため、連絡先を一覧表にし、目にしやすい場所に貼っておくと安心です。