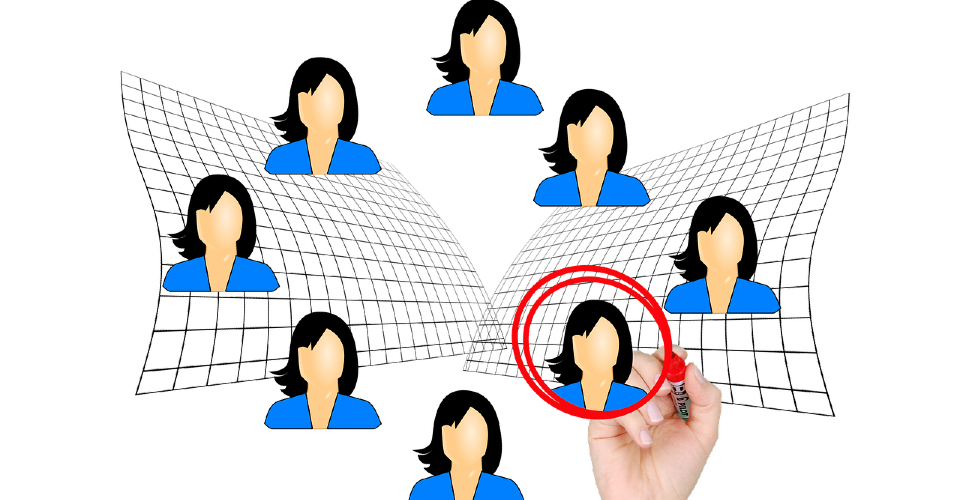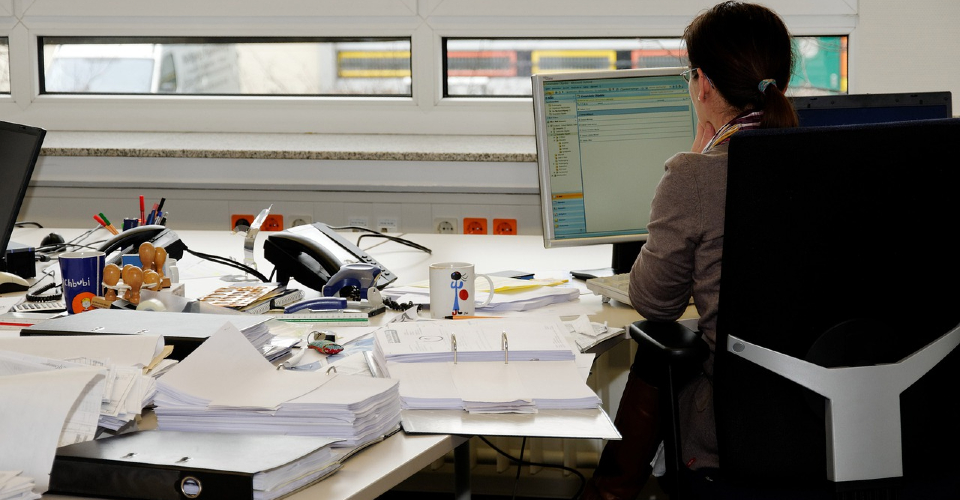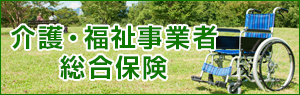介護施設において必要な福祉サービス第三者評価事業とは?

介護施設が質の高い福祉サービスを提供するため、中立的な立場や専門的・客観的な視点において第三者機関による評価を実施する「福祉サービス第三者評価」という仕組みをご存じでしょうか。
福祉サービスを提供する事業所は多種多様にあり、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、障害者支援施設、社会的養護施設、そして保育所なども含まれます。
これらの福祉サービスを公平に評価する仕組みですが、具体的に福祉サービス第三者評価事業とはどのような内容なのかご説明します。
利用者が安心して介護施設を選ぶ参考に
日本にある福祉サービスをより質の高いものへするために、介護事業所などの福祉・介護施設に対して第三者が評価を行う仕組みが福祉サービス第三者評価事業です。評価結果は公表されることとなり、福祉サービスを利用する方へ情報提供されています。
利用者が安心して介護施設などを選ぶときの参考になる仕組みともいえるでしょう。
なぜ第三者評価が必要なのか
介護保険サービスなどは契約による利用制度に移行していくことになりますが、介護事業者が質の高いサービスを提供していなければ、利用者から選ばれることはありません。
そのため、介護事業者は運営において何が具体的な問題となっているか把握し、サービスの質を向上させて、利用者が適切にサービスを選ぶことができるようにすることが必要です。
事業者の良いところや努力したほうがよい点を指摘することを目的としており、優劣をつけることを目的としているわけではないとされています。
介護施設が第三者評価に取り組むメリット
第三者評価に介護施設が取り組むことで、利用者に対する介護サービスの質向上に積極的に取り組んでいることをアピールできます。
また、評価における調査により、業務の課題を発見できるので組織全体の質向上につながることでしょう。
介護施設の経営者は、提供するサービスの内容の専門的で客観的な評価を受けることができるため、現状把握や課題を明確にし、改善させることができます。
第三者評価と行政監査の違い
行政監査の場合、法令による最低基準を満たしているかを所轄の行政庁が定期的に確認を行います。第三者評価は福祉サービスの質をよいものに改善させることを目的としているので、最低基準を満たしているかではなく、質の向上を目的としているというものであり、根本的な性格そのものが異なるといえるでしょう。
社会福祉法では、社会福祉事業の経営者のサービスの質向上に努めなければならないことと自己評価は努力義務としています。