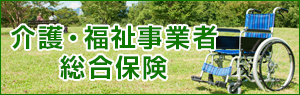介護事業者が知っておきたい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

2015年に介護保険が改正されたことにより、高齢者が要介護状態になってしまうことを防ぐ「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」が創設されました。
そこで、総合事業とはどのようなサービスが提供されるのか、その内容などをご説明します。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の特徴
従来までも市区町村で介護予防事業は行われていましたが、要介護認定を申請した後に自立となった高齢者がその対象でした。しかし総合事業の場合には、要介護認定を申請する必要なく利用できます。
要介護者や要支援者に対する全国一律の介護保険サービスと違って、市区町村が主体となり実施する事業のため、サービス運営基準・単価・利用料などは市区町村ごとに独自に設定されます。
介護保険から切り離された要支援に対する介護予防給付の一部(訪問介護・通所介護)に、それまで市区町村で行われていた介護予防事業が一緒になり、編成によって見直しが行われできた制度です。
要支援者と、65歳以上のすべての高齢者が対象であるため、これまでの介護サービスだけで支えることのできなかった高齢者にもサービスを提供できるといえます。
介護事業者が行う介護予防サービスだけでなく、NPO団体や民間企業、ボランティアといった様々な団体が主体となりサービスを提供していくのも特徴です。
総合事業とは
総合事業を大きく分けると、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分類されます。
介護予防・生活支援サービス事業
要支援者に対する訪問介護と通所介護(デイサービス)、そして介護予防や生活支援が必要な高齢者に対し訪問型と通所型のサービスを提供します。
要支援者に対する訪問介護とデイサービスは、それまでの介護保険制度から移行されたものとなっています。
利用対象者は要支援者で、高齢者が自身で生活機能が低下していると感じる部分にチェックを入れる「基本チェックリスト」という質問用紙で該当する方です。
総合事業以前の介護予防事業でも基本チェックリストはありましたが、要介護認定を受けて自立とされた方が対象でした。
総合事業の基本チェックリストでは、要介護認定を受けなくても、サービスの利用を希望する65歳以上の高齢者なら受けることが可能です。
一般介護予防事業
介護予防教室・体力づくり教室・高齢者向け講演会・サークル活動などを受けることができますが、対象となるのは地域に住む65歳以上のすべての高齢者です。もちろん要介護者も含まれます。