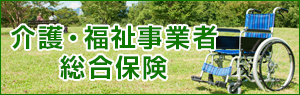介護事業者が注意しておきたい大企業病とは?治すために必要なこと

大企業病とは、企業の規模に関係なく、会社の風通しが悪いことや意思決定に時間がかかる状態を指しています。
規模の大きな大企業では、社員数や部署数なども多いため、風通しも悪くなり縦割り組織なので最終的な意思決定まで無駄な時間もかかります。
しかし大企業だけではなく、中小企業・ベンチャー企業でも起こりうるのが大企業病ですので、介護事業者も施設内で発生していないか注視しておいたほうがよいでしょう。
大企業病を治すために必要なこと
大企業病に明確な定義があるわけではありませんが、放置していれば介護事業所の運営そのものが困難になる可能性もあります。
そこで、大企業病だと感じるときには、次の方法で改善させていきましょう。
上層部から人員刷新する
思い切った改革として、意思決定権のある上層部を一新することや、形骸化したルールは取り払うといったことが必要です。
安定志向の事なかれ主義のままでは、古い上層部がいつまでも在籍することになり、社内風土も変わりません。
上層部が変わる姿勢を見せれば、現場で働く社員も組織改革が本気であることを感じ取り、事業所を変えていこうとするでしょう。
業務改革で意思決定を迅速に
古い考えに囚われたままでは、何を目的としているかわからないルールに縛られることになり、意思決定まで時間がかかってしまいます。
スピード感を出すためにも、業務効率化を推進し、紙媒体の書類からデジタルへ変更するといったことも積極的に取り入れるべきです。
社内の風通しを改善させる
停滞した雰囲気を変えれば社内の風通しは良くなります。コミュニケーションを活性化させ、情報共有できる取り組みや工夫を取り入れるべきです。
社内SNSやビジネスチャットツールなどもその例ですが、交流を図るイベントを企画することも方法として検討するとよいでしょう。
ビジョンは明確に
社内が一丸となり、同じ方向を向き進んでいくことができれば、組織規模が拡大した場合でも大企業病は起こりにくくなります。
そこで、ビジョンや経営指針を現場にも浸透させるため、まずは明確化させ目標として周知していきましょう。
顧客ニーズを優先
現場のスタッフが内向き体質で、上司の顔色をうかがってばかりでは、大企業病になってしまう可能性は高くなります。
利益を追求するためにも、利用者の声に耳を傾け、顧客ニーズを優先させる姿勢が大切です。
上司ではなく顧客ニーズを優先させていける体制を整備していきましょう。