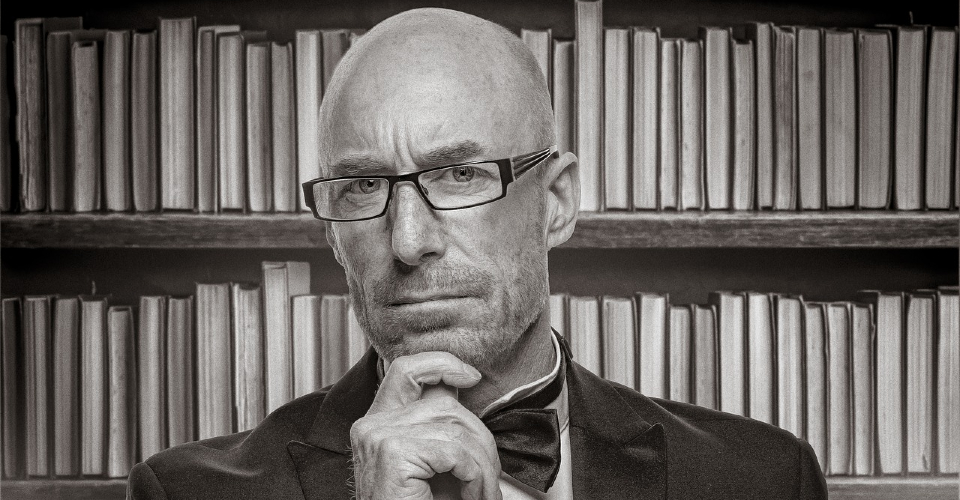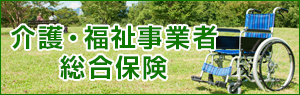延命治療とは?終末期ケアにおける必要性とメリット・デメリットを解説

日本は高齢化が進んでいるため、終末期医療に対する必要性が高まっているといえますが、延命治療についても理解を深めておくことが必要です。
医療機関などでは、終末期で病状回復が見込めないとき、本人やその家族が命をつなぐ「延命治療」を選択するか迫られることがあります。
本人の意思表示ができなくなってしまってからでは、延命治療を希望するか確認できなくなるため、終末期の対応について事前に家族で話し合っておくことも必要となるでしょう。
そこで、延命治療とはどのような治療なのか、終末期ケアにおける必要性とメリット・デメリットについて解説していきます。
延命治療とは
「延命治療」とは、老化に伴って心身が衰弱してしまったときや、重度の病気で生命維持が厳しい状態になったときに、医療措置によって一時的に命をつなぐことです。
医療技術が進歩したことで延命治療も可能になっている一方で、本人の意思に添っていない場合もあります。
そのため無理な延命治療はせず、痛みや不快感などを取り除く緩和ケアを行いながら、ごく自然な形で人生の最期を迎えるケースも増えてきました。
延命治療の処置として、
・人工呼吸
・人工栄養
・人工透析
などが挙げられます。
延命治療のメリット
延命治療のメリットは主に以下の2つです。
・付添など不要になる
・終活まで猶予ができる
それぞれ説明していきます。
付添など不要になる
延命治療は病院など医療機関に入院して行うため、見守り・服薬管理・付き添い・食事提供などの日常生活をサポートする必要はなくなります。
終活まで猶予ができる
延命治療は死期をコントロールする処置ともいえるため、財産や所有物の処分や相続など、終活に時間をかけることができます。
延命治療のデメリット
延命治療のデメリットは主に次の3つです。
・本人の意思に反する場合がある
・医療費負担が高額になる
・精神的負担が大きい
それぞれ説明していきます。
本人の意思に反する場合がある
延命治療を本人に意思決定が難しい状態で行う場合、本人の意思と関係なく実施されることになるため、意思に反する場合も出てきます。
医療費負担が高額になる
延命治療は高度な医療管理下に置かれることになるため、入院費用も高額になりやすいといえます。
高額療養費制度が適用されても出費が多額になることは避けられません。
また、いつまで続くのか予想できないため、終わりのないことが不安となる可能性もあるといえます。
精神的負担が大きい
本人に意識がない状態が続けば、家族の精神的な苦痛につながる可能性もあります。
さらに家族の判断で延命治療を止めたときには、自責の念に駆られる可能性もあると考えられます。