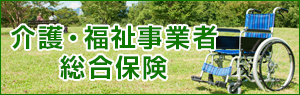自立支援とは?介護におけるサポートの方法について簡単に紹介

自立支援とは、介護を必要とする要介護者が、自らの能力に応じた生活を送ることができるためのサポートを行うことです。
介護現場でも、利用者が自分でできることまで取り上げてしまうのではなく、本人ができることはしてもらうことで能力維持や向上を図ることができます。
そこで、自立支援とは具体的にどのようなことを行うのか、介護におけるサポートの方法について簡単に紹介していきます。
自立支援とは
「自立支援」とは、次の取り組みを行うことといえます。
・高齢者が住み慣れた地域で能力に応じた日常生活を営むことができる支援をすること
・高齢者が意欲を持って潜在能力・強み・できることなどを最大限発揮できる支援を行うこと
・要介護状態を軽減または悪化させない支援を行うこと
要介護認定を受けた方の自立を支援することは、要介護者と介護者のどちらの負担も軽減できることであり、認知症予防にもつながります。
結果的に、その方が自分らしい生き方をすることにつながるともいえるでしょう。
介護現場における自立支援の方法
介護場面における自立支援の方法として、主に次の3つを意識することが必要です。
・介助し過ぎない
・生きがいを持ってもらう
・明確な目標を設定する
それぞれ説明していきます。
介助し過ぎない
利用者の残存機能を活かすことができるサポートが重要です。
できることまで取り上げれば、残った機能も低下してしまいます。
介護する側、受ける側の両方のストレス軽減にもつながるため、できることは本人に任せるといった意識でサポートすることが大切といえるでしょう。
生きがいを持ってもらう
たとえば利用者が施設での生活で何らかの役割を持つことができれば、それが生きがいにつながる可能性もあります。
得意なことを任せることなどで、自分にしかできない仕事や役割だと意識してもらうことができ、任されることに喜びを感じてもらえることもあるでしょう。
生活意欲や自発性の向上につながり、利用者同士のコミュニケーションも活性化します。
明確な目標を設定する
たとえば機能訓練などにおいて、自立支援という大きな目的を目標とするのではなく、何を実現させたいから行うのか、明確に目標を設定しましょう。
利用者が実現させたいことを目標やゴールとして決めておくことで、積極的な取り組みへとつながると考えられます。
やらされているのはなく、自主的に取り組むことで、生きがいやモチベーションにつながっていくでしょう。