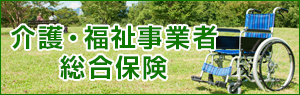介護事業者が安全配慮義務違反を問われないために必要なこととは?

介護事業者が気になるのは、もし介護施設などで事故が発生したときに安全配慮義務違反を問われ、責任を追及されないかということでしょう。
民事上の責任のうち、介護事故で問題となりやすいのが安全配慮義務ですが、どのような義務を守らなければならないのか説明していきます。
介護事業者が安全配慮義務違反と判断されるときとは
介護事業者の安全配慮義務とは、利用者の生命や身体、財産などの権利や利益を侵害せず安全に介護サービスを提供することです。
仮に安全配慮義務違反と判断されれば、利用者の損害を賠償しなければならなくなります。
介護事業者が守らなければならない安全配慮義務を確認するとき、医療業界の最高裁の例を参考にするとよいでしょう。
医療過誤の注意義務についての過去の判例を見ると、最高裁では注意義務の基準は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準としていました。
これを介護現場にあてはめた場合には、介護事業者が実践する必要のあるリスクマネジメント・対策・注意を怠っていたときに安全配慮義務違反とされると考えられます。
安全配慮義務違反を問われないために必要なリスクマネジメント
実際に介護施設で事故が起きたとき、その責任が誰にあるのかという判断は、利用者の状態や事故の原因により異なってくるでしょう。
そのため介護事業者の安全配慮義務違反の有無は、事故の事例ごとに検証し、評価しなければならなくなります。
いずれにしても介護事業者が安全配慮義務違反を問われないようにするためには、リスクの把握と確認するためのヒヤリハット収集とその情報共有が大切です。
介護スタッフから収集したヒヤリハットを分析し、どこに問題があったのか原因を洗い出しながら、見直しできる部分から改善させていきましょう。
改善させるためにも、
・リスク発生の原因そのものを取り除くこと
・事故が発生する確率を低減させるためにまずは損害の程度を軽減できる対策を講じること
・リスクが現実にならないように保険をかけること
などで備えることも必要です。
これらのリスクマネジメントを徹底して行い、一度対策すれば終了ではなく、実際にどのくらいの効果が見られたのか分析していきましょう。
もし改善できていないなら、他によい方法はないか、他にも隠れている問題の有無などを確認していきます。
この分析・検証・見直しを継続して行いながら、その時々で最適といえる対策を立てることが必要です。
日々の地道な努力や積み重ねが必要となりますが、介護事業者が安全配慮義務違反を問われないためには欠かせないことと捉え、継続させるようにしましょう。