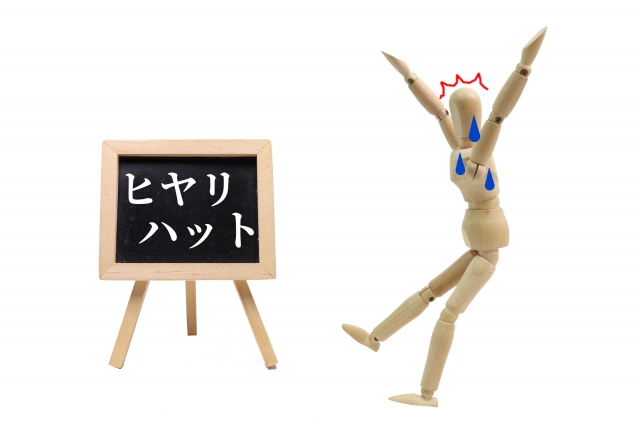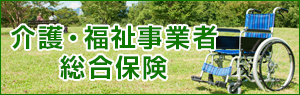介護保険料を滞納し続けた場合の制裁とは?払えないときの対処法も解説

介護保険料を滞納し続けた場合には、滞納期間に応じた負担額が増えることになります。
そしていずれは介護サービスを利用できなくなるため、滞納は早めに解消するべきといえるでしょう。
そこで、介護保険料を滞納し続けた場合の制裁としてどのようなペナルティを受けるのか、払うことができないときにはどうすればよいのか、その対処法について解説していきます。
介護保険料未納は滞納処分の対象
介護保険料の未納が続くと、滞納処分の対象となります。
納付期限を過ぎると、行政から郵便・電話・訪問で督促があり、財産の差押えを行う旨の内容を通知する催告が届きます。
督促の期限を過ぎても支払いがなければ延滞金が発生し、滞納期間が長くなるほど介護サービスの自己負担割合も高くなります。
滞納期間が長引いた場合の措置
介護保険料の滞納期間が長引いてしまったときには、次の3つの措置が取られることになってしまいます。
・連帯による支払い
・給付の制限
・財産の差し押さえ
それぞれ説明します。
連帯による支払い
年金年額18万円以下の方が滞納した場合には、配偶者や世帯主が連帯して保険料を支払わなければなららないという義務が生じることになります。
給付の制限
滞納が長引いた場合には介護サービスの給付制限により、介護サービス利用時の自己負担軽減が滞納解消まで一時的に止まります。
財産の差し押さえ
滞納が続き未納のままでは、いずれ財産を差し押さえられることになります。
対象となる財産は預貯金や生命保険などの金融資産が多いようです。
減免してもらえないか相談も必要
65歳以上で第1号被保険者の介護保険料は自治体ごとに決められることになり、原則3年に1度は見直しがあります。
令和元年に消費税率10%に引き上げられたため、住民税非課税世帯を対象として65歳以上の介護保険料も軽減されることとなり、第1~9段階まで設定されています。
もしも災害や失業などで収入が減少したなど、特別な事情で保険料を納めることが難しいのなら、減免や猶予など受けることができる場合もあるため相談してみましょう。
今は介護サービスを利用していない場合でも、介護保険を滞納していれば高額な延滞金を負担することになります。
支払わなければならない費用がどんどん増えることになるため、督促状が届く前に納めることが必要であり、支払いできないときには早めに相談することが必要です。