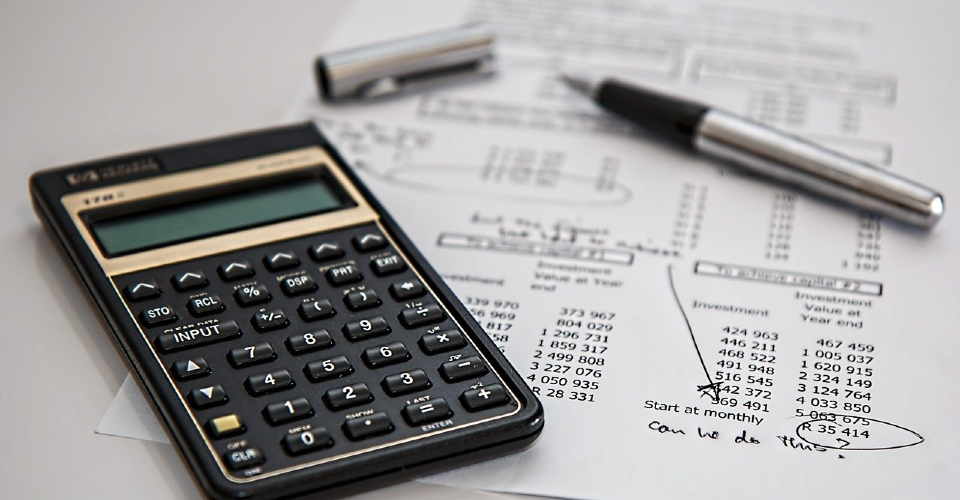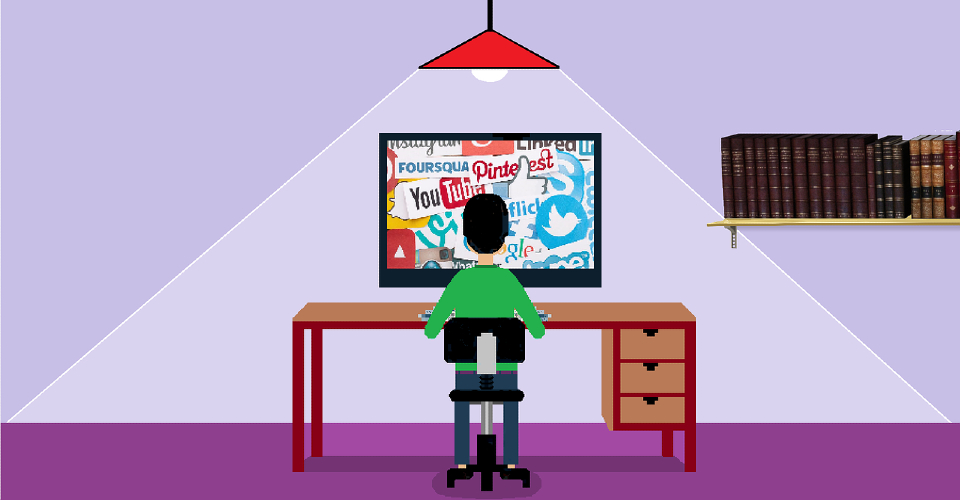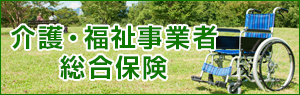介護離職とは?問題点や介護を理由に仕事を辞めることを防ぐ制度について解説

家族の介護が必要になった方が、仕事と両立することが難しいと判断し、退職してしまう「介護離職」が増えつつあります。
介護離職は、後々色々な問題を起こすことになるため、できるだけ介護離職者を減らすことが必要です。
しかし何が問題や原因になっているのか理解しておかなければ、効果的な対策など進めることはできません。
そこで、介護離職の問題点や、介護が理由で仕事を辞めることを防ぐ制度などを解説していきます。
介護離職とは
「介護離職」とは家族が要介護状態になったことで、介護に専念するため本業を辞めてしまうことです。
要介護者が施設に入所するのではなく、在宅介護を望むケースも少なくありません。
また、金銭的な問題により在宅介護を選ぶこともあるでしょう。
しかし在宅介護が必要になれば、配偶者や子が介護を担当することになります。
また、介護を必要とする方は高齢者であるため、その配偶者も高齢であることが多く、老老介護になりがちといえます。
現役世代の子が介護を担当する場合でも、兄弟姉妹で分担できず、一人が抱え込むことで介護離職を余儀なくされるケースがあるようです。
介護離職後の問題点
介護を理由に仕事を辞めてしまうと、当然、安定した収入が途絶えることになります。
現在の収入だけでなく、将来受け取る退職金がなくなり、年金も減ってしまうため経済的なデメリットしかありません。
介護者の貯蓄や親の年金に頼りながら生活をしていても、介護者自身の老後資金の備えはできなくなってしまいます。
介護保険を利用すれば、介護に必要なコストは抑えることができるでしょう。
しかし、紙おむつや防水シーツなど介護用品なども必要であるため、想定していたよりも経済的なつらさを感じることは少なくないといえます。
そのため、介護離職を検討するときには、その後の経済的なリスクを把握しつつ、将来の財政計画など立てることも必要です。
介護離職を防ぐ制度
介護離職は社会問題化しつつあるため、厚生労働省でも「介護離職ゼロ」を掲げ、次のような支援を行っています。
・介護休業制度
・介護休業給付
それぞれの支援について説明していきます。
介護休業制度
「介護休業制度」とは、2週間以上に渡り介護を必要とする家族がいる場合、介護を目的とした休暇を取得できる制度です。
1年以上雇用されていることなど条件を満たすことで、対象家族1人につき3回・通算93日まで休暇を取得できます。
介護休業給付
「介護休業給付」とは、上記の介護休業中に受給できる給付金で、次の要件を満たすことで受け取ることができます。
・雇用保険の被保険者であること
・家族の常時介護が2週間以上必要な状態であること
・職場復帰を前提とした介護休業を取得すること
以上の要件を満たせば、最長93日を限度に3回まで支給されます。