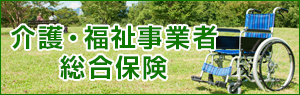日本の介護施設も北欧式の介護に対する考え方が必要?

高福祉・高負担として知られている国、スウェーデン。このスウェーデンは幸福度調査でも常に上位に位置する国ですが、住むことに幸せを感じられる国であることを象徴するかのように、寝たきりゼロの社会を実現させています。
そこで、スウェーデンをはじめとする北欧式の介護サービスとはどのような考え方なのか、日本の介護施設にも必要となるのかご説明します。
スウェーデンの介護施設の特徴
実際、スウェーデンのある介護施設では、施設で過ごすほとんどの方が80歳以上の後期高齢者で、さらに8割以上の方が認知症です。
しかし寝たきり状態の方は一人もおらず、自力で起き上がりができない方も介護スタッフが車いすに移乗させ食堂で食事をとるといった形です。
車いすの方も服を着替え、パジャマ姿で過ごすことはなく、日本の後期高齢者が生活する施設と比べたときに明るく穏やかな雰囲気を感じられることが特徴となっています。
本人の意思を一番に尊重し、散歩に出るときも本人が一人がよいといえば家族の同意を得て、GPS付きの携帯を持ってもらい許可を出すという形です。仮に本人が途中事故に遭ったとしても、自己責任の範囲で行動してもらうことになっています。
ベッドにしばりつけることもせず、お酒を飲みたいという方がいれば健康上の問題がない場合は飲んでもよいことにするなど、人生を楽しむことを可能とするサポートを行う施設として運営されていることが特徴といえるでしょう。
無理な介助は行わない
スウェーデンなど北欧諸国では、自らの口で食事を取ることができなくなった高齢者に対しては嚥下訓練が行われ、それでも難しい場合でも無理な食事介助や水分補給は行いません。
あくまでも自然な形で看取ることを行っています。胃に栄養を直接送る胃ろうなどは、むしろ虐待だとみなされていることが特徴です。
日本では亡くなる間際まで点滴やカテーテルを使い、静脈栄養などで延命措置が取られています。チューブだらけの姿になってベッドに横たわり、身動き取れない状態でも長生きさせるという考え方が一般的です。
自宅で最期を迎えたいと考えていても、施設と病院を行来し最終的に病院で亡くなるケースが多いといえるでしょう。
しかしスウェーデンなどでは過剰な医療は行わず、住み慣れた家や施設で最期を迎えることが一番だと考えます。
介護される側だけでなくする側も、その方が寝たきりにならない努力を行い、どうにもならなくなればそれは死が近づいたサインと考え、潔くあきらめることが北欧式の死の迎え方なのです。
スウェーデンでは介護スタッフは安定した職種
そして日本では介護スタッフといえば薄給で過重労働というネガティブなイメージが強いですが、スウェーデンでは安定した公務員であり経済的に困窮することもありません。
認知症の方が徘徊したことで鉄道事故が発生し、遺族が鉄道会社から損害賠償を求められるといった裁判もありましたが、スウェーデンでは考えられないのです。
スウェーデンでは介護の費用はすべて国や自治体が負担するので、家族が介護で経済的負担を強いられることもないとされています。
老老介護や老後破産に孤独死など、介護に関する問題が深刻化する日本では、このようなスウェーデンの考え方も一部取り入れていくことが必要なのかもしれません。