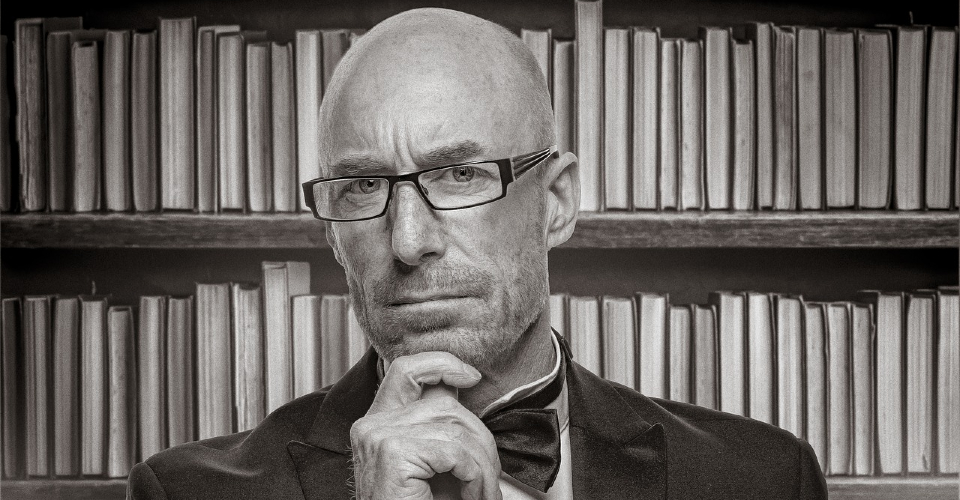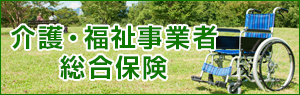介護事業者が提供するサービス以外で地方自治体独自が行う家族支援事業とは?

介護保険制度を利用すれば、介護事業者が提供する福祉用具をレンタルできたり介護を受けたりできますが、介護をしている家族を対象とした支援を地方自治体が行っているケースもあります。
そこで、介護者である家族を対象とした地方自治体の家族介護支援事業とはどのような内容なのかご説明します。
家族介護支援事業は地方自治体ごとに内容が異なりますが、主に介護をしている家族を対象としており、介護保険制度だけではカバーできない部分が補充されていることが特徴です。
地方自治体ごとに異なる家族介護支援事業
地方自治体によって家族介護支援事業の内容は異なりますが、たとえば次のような事業内容が行われています。
家族介護用品支給事業
地方自治体が介護用品を支給する交付券を提供し、設定された月額または年額の上限範囲で介護用品を支給する制度です。
たとえば紙オムツ・尿取りパット・使い捨て手袋・ドライシャンプーなど衛生用品がその対象となります。
家族介護慰労金支給事業
所得が低い方が可能な限り自力で在宅介護したいものの、様々な理由で介護保険サービスを利用していないときに年額10万円など一定金額が支給されるという事業です。
家族介護教室
介護方法や介護についての知識、介護をしている家族の健康や介護予防について学ぶ教室です。高齢者の食事と栄養、健康管理、認知症の方の介護や予防などを学習します。
家族介護継続支援事業
施設見学や日帰り旅行など活用し、介護をしている家族同士が交流できる場を提供して心身を元気にする事業です。
寝たきり高齢者とその家族に対する支援
要介護3以上の寝たきりの在宅高齢者に対する理髪・美容サービスや、寝具の洗濯・消毒・乾燥まで行う寝具洗濯サービスなど、決められた回数以内で利用できる支援事業です。
他にも在宅の寝たきり高齢者を介護している家族に介護手当を支給するといった事業もあります。
高齢者緊急通報システム事業
徘徊のリスクが高い高齢者の早期発見を地域で支援する事業で、認知症の高齢者など徘徊行動が見られる方やその介護をしている家族を対象とし、緊急通報システム用機器を貸与しています。
高齢者外出支援事業
65歳以上の方だけで構成されている低所得世帯などを対象とし、タクシー・バス・船舶で利用できるチケットを支給する事業です。定められた年額上限の範囲で利用が可能となっています。
福祉電話貸与事業
電話を設置していない方などを対象とし、電話設置による各種動産・連絡などを事業として行っています。