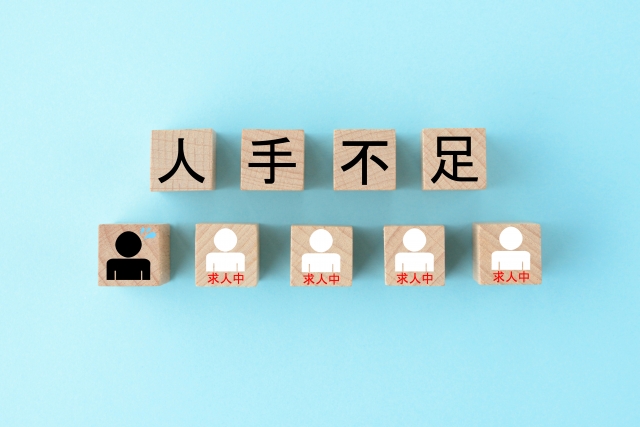建設工事の今後のビジョンは?ITやAI導入は進むのか

建設工事を行う業界で働く職人は、2025年には35万人超が不足するといわれています。
不足するだけでなく高齢化も深刻さを増している中で働き方改革も求められているため、生産性向上に向けてどのように取り組んでいけばよいのか、そのビジョンを立てていくことが必要です。
建設工事現場で働く職人が不足している問題は、今にはじまったことではなく長年問題視されてきました。若年層の入職希望者は増えず、今働いている方も高齢化しており、このままでは現場の職人はいなくなってしまうことが懸念されている状況です。
その限られた人材の中で、どのように生産性を向上させていくか課題として考えなければなりませんし、人手不足の解消に向けて建設業界のビジョンを捉えていかなければなりません。
建設技能者は若年層が減り高齢化
建設業界は人手不足に技能者の高齢化などのイメージが強く、若い世代に魅力を伝えたくても魅力そのものが不足していると考えられます。
総務省の調査による建設技能者人口は、1997年時点は464万人でした。しかし2014年には343万人に減少し、今後2025年には215万人程度になってしまうことが予想されています。
長期ビジョンでみても、2014年度は50歳以上だった技能者が153万人います。その方たちが2025年に離職することになれば、全体の7割強にあたる109万人がいなくなってしまうのです。
人手不足に高齢化する職人への対応に向けて、日建連でも2025年までに90万人、新規入職者を獲得することを目標としています。
不足する35万人については、省力化技術でカバーしようという取り組みも見られます。
人手不足解消と業務効率化に向けたITやAIの導入
国内の人手不足や業務の効率化への対策としてITやAIを導入する例として、
たとえばIT導入については、
・自動作図ソフトを導入すること
・タブレット端末で現場を一括管理すること
・ホロレンズで3D完成イメージを共有すること
・工事作業員の代わりにロボット技術を導入すること
などが具体的に挙げられます。
AIについては大手ゼネコンなどで試作として次の技術開発などが進められています。
・予算や要望に応じたプロジェクトを提案
・熟練工の技術に代わる微妙な機械操作
働き方改革前進にもつながる?
建設現場や設計などで時間を必要とする作図作業やイメージの共有、書類作成にデータの共有・整理などがIT化されれば、業務効率化が実現し働き方改革も前進させることが可能になるでしょう。
働き方改革についても、建設業には5年間の猶予が与えられていますが、同時に国土交通省では建設現場の生産性を2025年までに20%向上させることを目標として掲げています。
生産性向上を向上させることも大切ですが、中小建設会社を巻き込んで取り組まなければ実現することは難しいと考えられています。