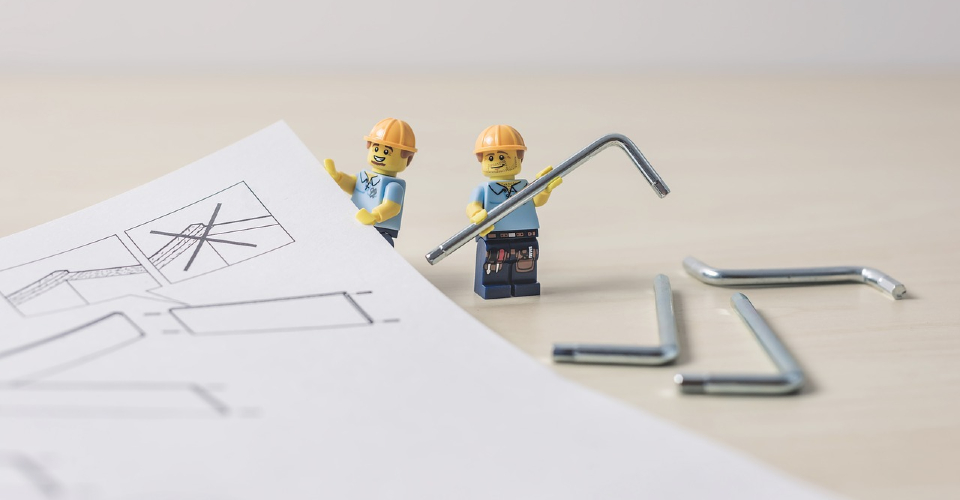建設工事業の作業員は建設国保ではなく社会保険に加入しなければならない?

建設工事業の作業員は、社会保険ではなく建設国保に加入しているケースも少なくありません。
建設工事業に携わる方のうち、個人事業所や一人親方であれば建設国保に加入できます。
建設業界は社会保険への加入が不十分であることを指摘されていますが、建設国保も社会保険と同様の保険です。
そこで、建設工事業の作業員は建設国保ではなく社会保険に加入しなければならないのか解説していきます。
社会保険への加入状況
建設業の社会保険への加入率は、100%とはいえません。
それは、建設国保に加入している作業員もいるからです。
ただし社会保険への加入状況については、以下のタイミングなどにおいて、国土交通省に確認されます。
・建設業許可・更新のとき
・指導や立入検査のとき
・経営事項審査・指名競争入札のとき
未加入の場合には、減点の対象となるため加入しておくべきといえるでしょう。
建設国保とは
建設業でも社会保険への加入は必要ですが、建設国保でも問題ないのでは?と疑問を抱く方もいることでしょう。
建設国保の運営元は全国建設工事業国民健康保険組合であり、国保が所得を基準に保険料を決定するのに対し、建設国保は家族構成や年齢を基準に保険料を決めます。
そのため通常の国保よりも保険料を抑えることができるといったメリットがあるため、建設業で仕事をする方でも建設国保に加入している方は少なくありません。
しかし社会保険への加入が強化されているため、わざわざ建設国保をやめてまで社会保険に加入するべきかと悩む方もいるようです。
社会保険は保険料を労使折半するため、現場の作業員が増えれば会社の負担も増えます。
さらに建設国保は所得ではなく年齢・事業所・就労形態・家族の人数などによって保険料が決まるため、保険料負担も抑えられるでしょう。
いずれにしても建設国保と厚生年金に加入することで社会保険加入の要件を満たすため、積極的に社会保険へ移行する必要はないといえます。
建設国保と厚生年金であればOK
健保適用除外の手続を行えば、建設国保と厚生年金への加入により、社会保険加入の要件を満たします。
事業者と作業員どちらの保険料に関する負担を見ても、無理に社会保険に移行する必要はないといえるでしょう。
しかし元請けなどが、社会保険を重視している場合は注意してください。
建設国保を脱退し、社会保険へ加入しなおすよう求めてくることもあるようです。
しかし社会保険加入要件を満たしている場合には問題ないといえるため、このようなケースにおいては建設労働組合などに相談することも必要となるでしょう。