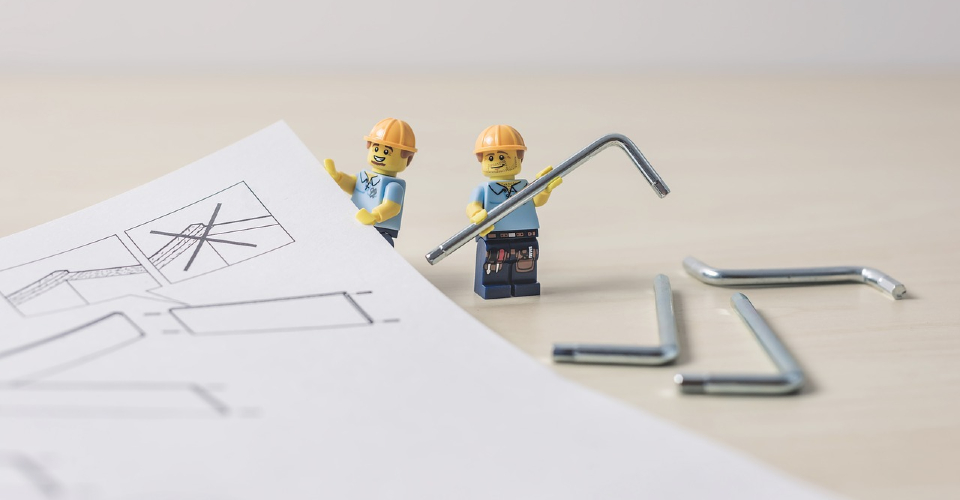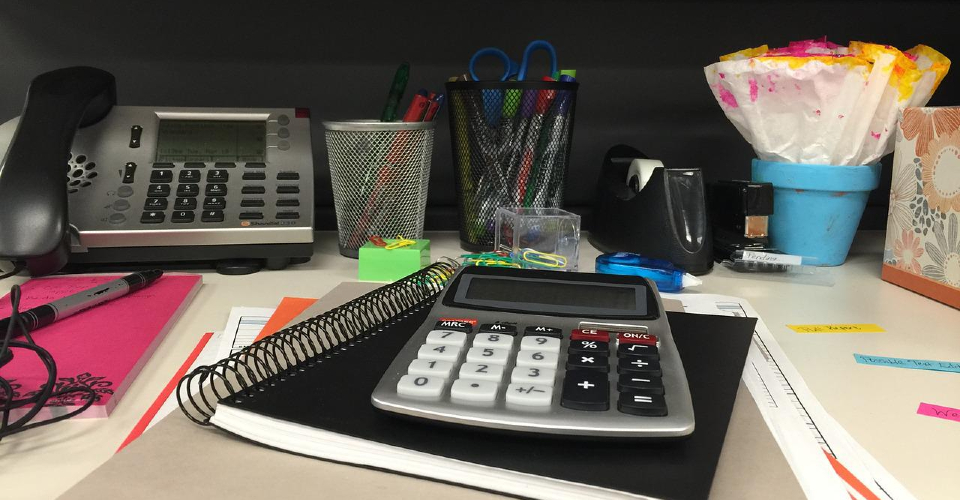一人親方が屋号を付けるときに押さえておきたいポイントと注意したいこととは

一人親方として建設業を営む場合、開業届を税務署で提出します。
そのとき、「屋号」はどうすればよいか悩んでしまう方もいるようですが、名刺にも記載される部分のため慎重に考えることが必要です。
そこで、一人親方が屋号を付けるときに押さえておきたいポイントと、注意しておきたいことについて説明していきます。
付けた屋号を使う場面
屋号を使う場面として考えられるのは、たとえば名刺交換や、取引先に請求書を発行するときです。
他にも購入したもの似たいする領収書を発行してもらうときや、振込指定の銀行口座を開設するときも屋号を使います。
普段は使うことがなくても、請求書や領収書など保管しておかなければならない書類などに記載することが多いといえるでしょう。
屋号を付けることは義務ではない
開業届には屋号を記入する欄がありますが、記載は義務化されていません。
個人で仕事をする方の中には、屋号ではなく個人名のほうがよいという場合もあるため、無理に付けなければならないわけではないとされています。
屋号の付け方
一人親方が屋号を付けるとき、付け方として次の2つを押さえた上で考えるようにしてください。
・業務内容がわかりやすい屋号を選ぶ
・禁止されているワードは使わない
それぞれ説明していきます。
業務内容がわかりやすい屋号を選ぶ
屋号を決めるときには、建設業であるなど業務内容が連想できることが理想です。
たとえば、
電気
塗装
土木
内装
建築
など、これから営む業種など専門分野を含めた屋号なら、名刺交換でも何の仕事をしているのかすぐに理解してもらいやすくなります。
禁止されているワードは使わない
屋号について、厳しいルールなどは特にありませんが、「会社」「法人」などのワードを含めることはできません。
法人でないのに法人と勘違いさせてしまう可能性があるからです。
また、商標登録されているワードも使うことができませんので注意しましょう。
商標登録されていれば特許と同様に、独占する権利が発生します。
そのため商標を屋号に使ってしまうと、不当に得た利益として損害賠償請求されてしまう可能性があるため十分に注意してください。
商標登録されている言葉か知りたいといきには、特許情報プラットフォームなどを活用すれば確認できます。
税務署などに問い合わせても教えてもらえないため、たとえ面倒でも確認することが必要です。