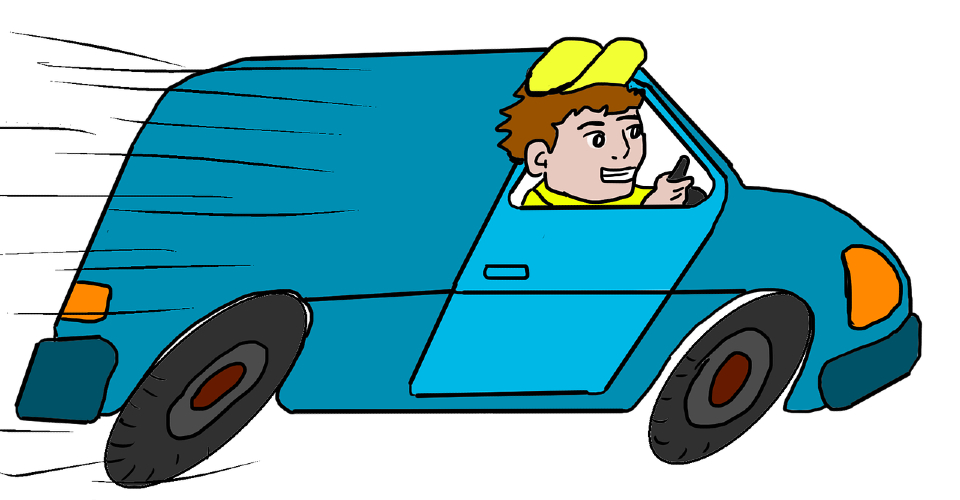運送業界の現在の宅配便取扱個数はどのくらい?個数増加で問題になっていることとは

現在、インターネットやECサイトの普及などにより、運送業の宅配便取扱個数は増えていると考えられます。
令和3年8月に公表された「令和2年度宅配便取扱実績」では、令和2年度のトラック運送と航空等利用運送の合計宅配便取扱個数は48億3,647万個であり、令和元年度と比べると5億1,298万個(約11.9%)増加していることがわかっています。
コロナ禍の影響なども関係していると考えられますが、宅配便取扱個数の増加の現状と、それにより起きている問題について説明していきます。
宅配便の取扱個数
令和3年9月に公表された「令和2年度宅配便取扱個数」を確認すると、トラック運送は47億8494万個、航空等利用運送は5153万個で合計48億3647万個でした。
前年度と単純に比べた場合、5億1298万個、11.9%の増えたことになります。
宅配便業界はヤマト運輸・佐川急便・日本郵便の大手3社が上位を占めますが、トラック運送は上位3便で94.8%、上位5便となる福山通運と西濃運輸を含めれば99.8%を占めることとなるため、実績に表れた構造だといえます。
宅配個数増加に伴って浮き彫りになった再配達問題
宅配便取扱個数は増加の一途をたどっているといえますが、コロナ禍の影響もあり急速に伸びています。
しかし配達の2割が再配達されるなど、コストの上乗せや時間がかかるなど、ドライバーの大きな負担になっているといえるでしょう。
地球温暖化の観点からもトラックから排出される二酸化炭素を削減することが求められ、再配達の削減が必要とされています。
そこで活用したいのが、
・配送日・時間指定
・置き配
・コンビニ受け取り
・宅配ボックス
などの代替手段です。
前もって日中は不在であることがわかっていれば、配達する日時を指定してもらうことで再配達を回避できます。
また、運送会社が提供するアプリやウェブサービスを活用した追跡で、荷物が現在どこにあるのか、いつ配達されるか予測してもらうこともできるでしょう。
コンビニでの受け取りや、駅や自宅の宅配ボックスを活用するといった方法でも再配達は回避されるでしょうし、玄関やメーターボックスなど指定した場所に荷物を届ける置き配などもだんだんと浸透しつつあります。
コロナ禍でネットショッピングを活用する人が増え、食料品や日用品などの個別配送が増えました。
宅配便取扱個数の実績や推移を見れば、今後も増加することが予想されるものの、物流機能の維持やドライバー負担の軽減のためにも再配達を削減する取り組みは欠かせないといえます。