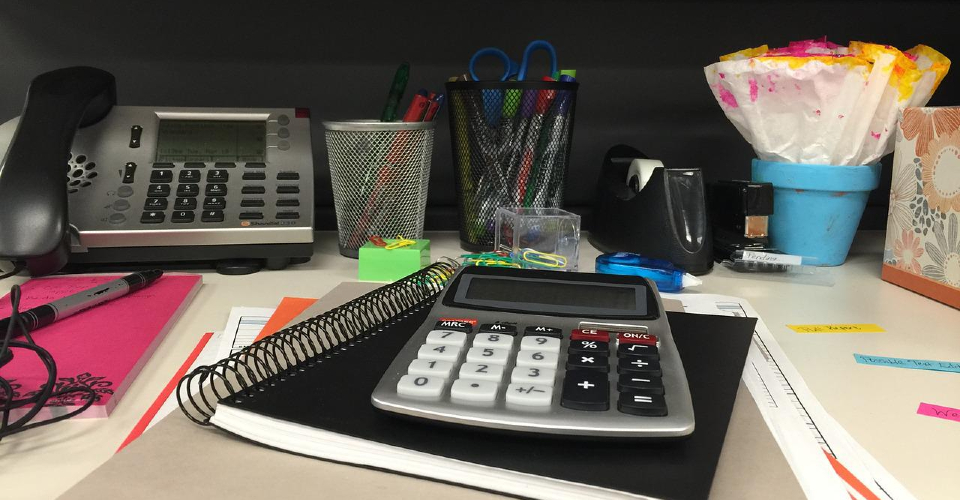運送ドライバーの労務管理は徹底して行うことが必要!

運送業で問題となっているのは、ドライバーが長時間労働で過労となり、健康障害や重大事故を起こすことです。
このような事態が起きないように、徹底して労務管理を行うことが必要とされています。
貨物自動車運送事業輸送安全規則にも、
「貨物自動車運送事業者は、休憩または睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転手にこれらを遵守させなければならない」
とされています。
違反すれば厳しい行政処分の対象となり、過去には事業許可取消となったケースあるため、十分労務管理には注意し徹底して行うことが必要です。
以前は長時間労働ではなかった?
運送業は他業種よりも長時間労働になりやすい環境にありますが、もともとは大手各社なども二人で運行するツーマン運行が主流であり、一般の小型集配車両にも配送助手が同乗する形式をとっていました。
しかし日本経済は1990年代後半から不況となり、物量の激減や燃料費高騰で経営に大ダメージを受けた各社が生き残りをかけて人員削減を行い始めてから状況は一変します。
追い打ちをかけるように、運送業界はきつい・汚い・危険という3Kのイメージが定着するようになり、若い世代から敬遠されるようになってしまいます。
その上規制緩和で新規に運送業界へと参入する業者は増え、荷物を奪い合う競争が激化し、仕事を獲得するため過剰なサービスを提供しなければならない状況を作ってしまったともいえるでしょう。
様々な悪循環で運賃は値下げされ、できるだけ荷物を効率的に配送するために、ドライバーの長時間労働が常態化してしまったといえます。
長時間労働で過労となったドライバーが重大な事故を起こしてしまうのも社会的な問題となりました。
ドライバーの労働時間の基準は徹底して遵守を
国やトラック協会も、このような事態を見過ごすわけにはいかず、積極的に改善するための取り組みを始めました。
平成元年2月に出された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」もその1つで、ドライバーの労働時間など労働条件を改善するための告示です。
ドライバーの拘束時間・運転時間・休息時間・休日労働などについて基準が定められることとなり、労務管理や運行管理はこの基準を遵守し行うことが必要となっています。
長時間労働で重大な事故を発生させないことやドライバーの健康管理のためにも、運行計画を見直すことが必要ですし、特定のドライバーに集荷時間が遅くなるコースを固定させないようにしてください。また、運転業務以外で残業はさせないことも必要です。