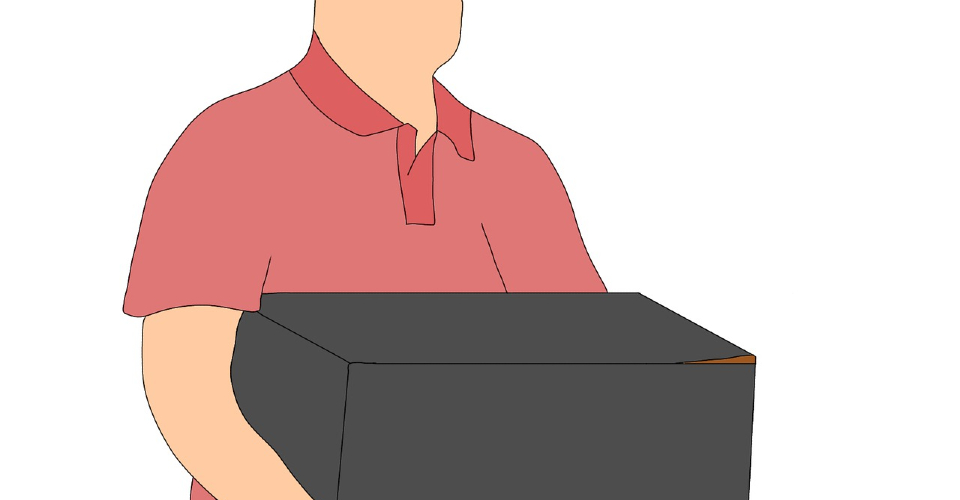貨物輸送の種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説

貨物を運ぶ運輸業の分野の1つに「貨物輸送」がありますが、なじみの深いトラックを使った貨物輸送以外では次の方法が挙げられます。
・貨車(鉄道)
・船(貨物船)
・飛行機
このうち、貨物鉄道輸送の特性は長距離・大量・低環境負荷といったことが挙げられます。
それぞれの貨物輸送ごとに特徴は異なり、利用するメリット・デメリットがあるため、その内容と注目される貨客混載やモーダルシフトについて解説していきます。鉄道貨物輸送の特徴
「鉄道貨物輸送」は、運ぶ距離が長く荷物量が多いほどその作業が効率化できる方法であり、鉄道ダイヤに基づいて安定した輸送が可能となります。
環境に優しくエネルギー効率も高いため、問題視されているCO2排出量削減にもつながることで注目されているといえるでしょう。
ただし鉄道ダイヤに基づくため、トラック輸送と比べると時間や頻度に融通が利かないことはデメリットといえます。
海上貨物輸送の特徴
「海上貨物輸送」は、大量の荷物を運ぶことができる上にそのコストも安いことが特徴です。
航空貨物輸送よりも運ぶ荷物の大きさや重量が制限されませんが、時間がかかることはデメリットといえます。
航空貨物輸送の特徴
「航空貨物輸送」は、船を使った輸送よりも運賃が高く貨物の大きさや重さに制限があることがデメリットである反面、荷物に対する衝撃が少なく輸送時間を短く抑えることができることがメリットです。
盗難などのトラブルも少なく安全に運べる輸送手段といえるでしょう。
貨客混載とは
「貨客混載」とは、乗客と荷物を一緒に輸送することですが、たとえば鉄道・飛行機・路線バス・タクシーなど旅客事業の一部のスペースを使って行われます。
2017年9月からは国土交通省も過疎地域でバス・トラック・タクシーなどの貨客混載を一部解禁し、2020年11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正によって貨客混載手続を迅速に行うことができるようになりました。
環境負荷軽減や物流コスト削減、配送需要増加への対応など様々なメリットがある反面、運搬量に制限が出ることや到着まで時間がかかること、1回の配送で関係する業者数が多くなることはデメリットといえます。
モーダルシフトの必要性
「モーダルシフト」は貨物輸送方法を転換することですが、これにより鉄道利用は90%、船舶利用80%のCO2排出量を削減できます。
地球温暖化対策として有効な方法であり、労働力不足解消や働き方改革の観点からも必要とされています。
ただしコンテナサイズに合わせた荷づくりが必要になることや、トラック輸送よりリードタイムが長くなるといった問題点を解消することが必要です。